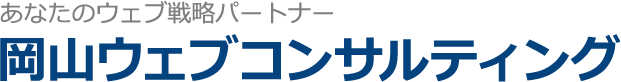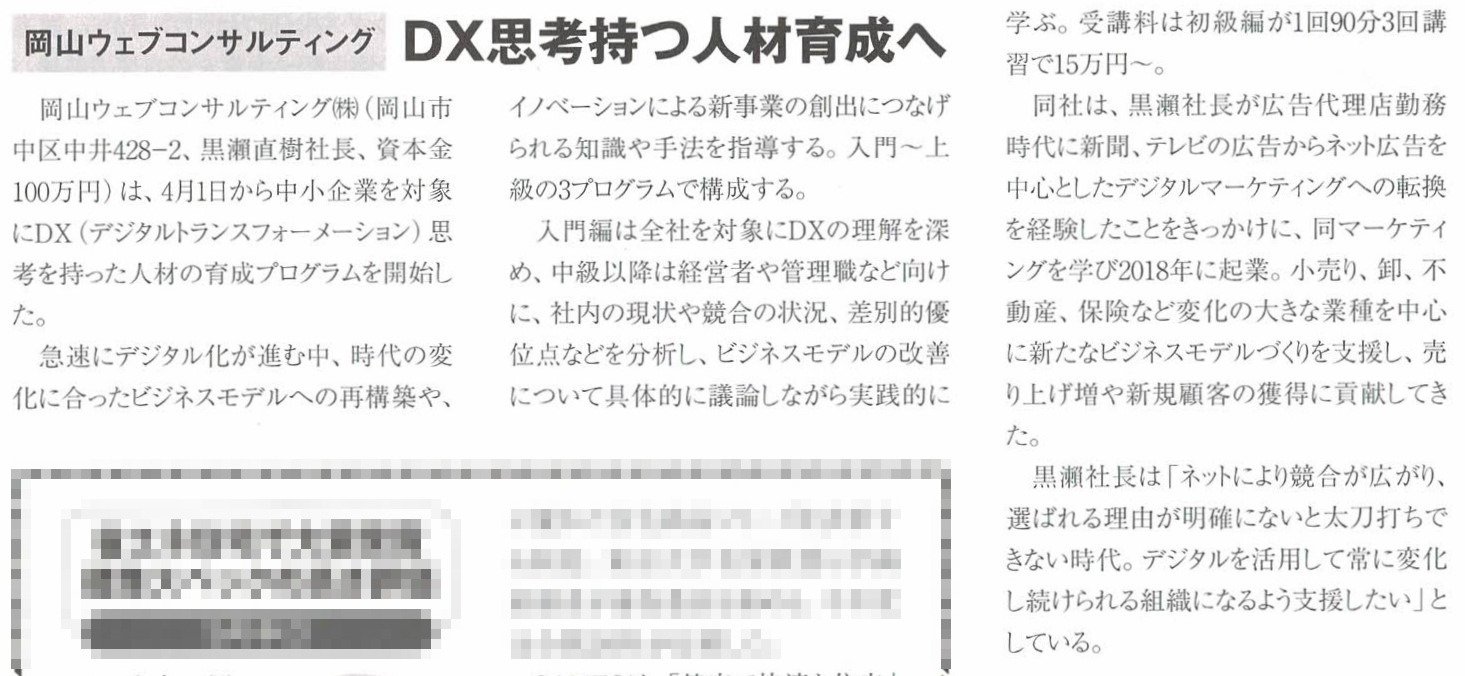
地元の経済情報誌ビジョン岡山に、DX思考育成プログラムを取り上げていただきました。
とても大きく掲載していただき、ありがとうございます!
昨年からお手伝いしている備商株式会社様では、これからのイノベーションに向けた新商品・サービスの社内コンテストを行っています。
先日は第二回目の経過発表会でした。
このコンテストでは会社のDXに向けて社内から5つのチームを選出し、それぞれが違った角度で提案を行います。
発表内容はもちろんAB3C分析を使っていただいており、
・お客様の絞り込み(STP)
・そのお客様のベネフィット(ニーズ・ウォンツ)
・自社の強み
・競合の強み
・差別的優位点
をチームで話し合い、ヒアリング調査などを進め、新しい商品やサービスを企画していきます。
会を増すごとに内容も濃くなってきていますし、
皆さんとても主体的に会社の未来像を考えていただけるようになってきたと感じます。
8月のコンテスト発表会ではどのような企画が出てくるか、とても楽しみです。
昨日は岡山東法人会で、こどもエコクラブ環境学習会のお手伝いをしてきました。
写真はKSBさんで放送された昨日のニュース映像。
1枚目の右上に小さく写っている司会をしているのが私です。
プログラムの1番目はコロッケ先生による紙の資源の授業。
古紙を使ってはがきを作るとても楽しい授業でした。
古紙50キロで、大木1本を守ることができるそうです。
2番目はてっちゃん先生によるチリメンモンスターと海洋プラスチック問題の授業。
どちらも大人の私が聞いてもとてもためになる内容で、参加いただいた子どもたちはもちろん、親御さんにとってもとても勉強になった内容だったと思います。
普段はフリートークが多い私ですが、逆に台本がある司会は苦手…
あまり噛まずに言えたので、ほっとしました。
DXというと自社のデジタル活用のことを指すことも多いですが、本質はデジタルによって起こった世の中の環境変化への対応。すなわち「デジタル社会に求められる自社の提供価値の変革」が必要です。
このあたりを動画にまとめましたのでご覧ください。